腰痛になったらこうしよう!腰痛を治すための手順
2020/1/27
こんにちは。
バレーボールスキルアップブログVBSUです。
このブログではバレーボール上達のための方法を勉強していくブログです。
技術的な部分の向上のためにはどう練習やトレーニングをすれば効率が良いのかを理解し、考え実行することが大事です。
ただやみくもに指導者の言うとおりにやるのではなく、本当にそのやり方でいいのかを考えることも場合によっては必要です。
さて、バレーボール選手で腰への痛みや違和感を感じたことがある人は世の中大勢いると思います。
重いものを持った時や、スポーツを頑張っていて練習中に痛んだり練習後に痛む場合もありますし、椅子に座っているだけで痛むという方もいるかと思います。
みなさんは腰痛に限らず捻挫のように足首を捻ったり、バンザイのように手を上げる動きで肩に痛みを感じたり階段の昇り降りで膝が痛かったりした場合はどうしていますか?
腰痛や膝痛などどこかしら痛みが出た時にとる行動パターン
・当院のような治療院や接骨院に行ってみる
・整体やもみほぐしのお店に行ってみる
・とりあえずそのまましばらく様子を見る
・痛み止めと湿布で気合で治す
・整形外科に行ってみる
・かかりつけにしている病院(整形外科以外)に行ってみる
だいたいこの中のどれかに当てはまると思います。
賛否あるかと思いますが、最優先で選ぶべき行動は整形外科にかかることだと考えています。
整形外科、接骨院、鍼灸院、整体など各施設の役割や特徴を見ていきましょう。
整形外科
整形外科は医師による診断を行う施設で簡単に言うと病院です。
日本整形外科学会のHPにはこのように書いてあります。
整形外科は運動器の疾患を扱う診療科です。身体の芯になる骨・関節などの骨格系とそれを取り囲む筋肉やそれらを支配する神経系からなる「運動器」の機能的改善を重要視して治療する外科で、背骨と骨盤というからだの土台骨と、四肢を主な治療対象としています。背骨と脊髄を扱う「脊椎外科」、上肢を扱う「手の外科」と「肩関節外科」、下肢の「股関節外科」、「膝関節外科」と「足の外科」、スポーツによるけがや障害を扱う「スポーツ医学」、「リウマチ外科」、腫瘍(できもの)を扱う「骨・軟部腫瘍外科」、骨粗鬆症などを扱う「骨代謝外来」と多数の専門分野があります。スポーツ傷害や交通外傷、労働災害などに代表される打撲、捻挫、骨折などの外傷学は勿論のこと、変形性変化を伴う加齢疾患、骨粗しょう症、関節リウマチ、痛風、運動器の腫瘍、運動器の先天異常など先天性疾患など、新生児時から老年まで幅広い患者層を扱います。
出典元:公益社団法人 日本整形外科学会
ざっくり言うと骨や筋肉などに異常がないかをレントゲンやMRIのような画像診断を使ってしっかり診てもらえる場所といったところでしょうか。
整形外科を受診することをためらう人からよく聞く話としては、
「待ち時間が長いのに診察がすぐ終わった」
このような意見が圧倒的に多いです。
それでも痛みが出た場合は骨や筋肉などに異常があって起こった痛みなのかを見極めるために整形外科はかかるべきです。
接骨院(整骨院)
接骨院は主に急性外傷(捻ったりぶつけたりした時)で受診する施設で健康保険が使えます。
よくトレーナー活動をしている時に中高生から「病院へ行ってきた」と言われよくよく聞いてみると接骨院だったということがあります。
接骨院は医師ではなく、柔道整復師という国家資格を取得している方が働く施設です。
柔道整復師とは
昔から「ほねつぎ」「接骨師」として広く知られ、現在は高校卒業後、都道府県知事が指定した専門の養成施設(三年間以上修学)か文部科学省が指定した四年制大学で解剖学、生理学、運動学、病理学、衛生学、公衆衛生学などの基礎系科目と柔道整復理論、柔道整復実技、関係法規、外科学、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修します。
国家試験を受け、合格すると厚生労働大臣免許の柔道整復師となります。
資格取得後は、実務経験と研修の受講により受領委任の取扱いが行える「接骨院」や「整骨院」という施術所を開業できます。また、勤務柔道整復師として病院や接骨院などで働くこともできます。
柔道整復師(国家資格)≠ 整体師、カイロプラクティック師(非国家資格)
柔道整復師(国家資格)≠ あん摩・マッサージ・指圧師(国家資格)
柔道整復師の業務
接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術を行っています。
最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。健康被害や金銭トラブルを被ることもあります。業務範囲を守って、良質で安心安全な施術ができる接骨院や整骨院にかかることが肝要です。
出典元:公益社団法人日本柔道整復師会
昔の接骨院では日中は高齢者の社交場的な状態となっていましたが、現在では徐々にそういった施設は減ってきているようです。
鍼灸院
はり師ときゅう師といった二つの施術を行う施設で、基本的には健康保険が使えませんが一部保険が使える疾患もあります。健康保険の使える疾患については以下の通りです。
神経痛…例えば坐骨神経痛など。
リウマチ…慢性で各関節が腫れて痛むもの。
腰痛症 …慢性の腰痛。
五十肩…肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
頚腕症候群…頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
頚椎捻挫後遺症…むち打ち症などの後遺症。
出典元:公益社団法人日本鍼灸師会
日本鍼灸師会のHPには上記の疾患で健康保険を使うための手順も書かれているので検討している方は参考にしてみてください。
また、鍼やお灸に関しては直接人体に鍼を刺したりお灸により熱を加えたりするので、痛みや熱さを嫌う方もいますが、鍼は髪の毛ほどの細さでさらに細いものもありますし、お灸も症状によっては温かさを感じる程度でとってしまうものもありますので相談すると良いと思います。
マッサージ
もみほぐしや整体で受けられるものと同じと勘違いをしている方が多いようですが、「あん摩マッサージ指圧師」といった国家資格所持者でなければなりません。
厚生労働省からの通達が日本あん摩マッサージ指圧師会に記載されていました。
内容は以下の通りです。
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。出典元:公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会
となっています。
最近よく見かけるもみほぐしのお店などはいずれ規制に合い営業できなくなる可能性もあるかもしれませんがどうでしょうか…?
整体・カイロプラクティック・もみほぐし
整体やカイロプラクティック、もみほぐしなどといった看板を掲げている施設は国家資格を所持していませんので本来「○○痛」などの疾患名を挙げての営業はできません。
カイロプラクティックはアメリカでは国家資格となっていてアメリカで取得し帰国後に開業している方もいるため腕の良い施術家ももちろんいます。
ですが日本においてはこれらは国家資格とされていないので素人同然の人が営業している可能性も十分考えられますのでご注意を。
まとめ
上記でも伝えたように腰痛になったらまずは整形外科の受診をオススメします。
整形外科での処置やリハビリで改善を目指しましょう。
また、リハビリへの力の入れ具合は整形外科により違いがあります。
もし整形外科であまりリハビリを行ってもらえないようであれば鍼灸やマッサージにかかると良いかもしれません。
かかりつけの接骨院や鍼灸などの治療院があればまずそこへ行き整形外科への受診の相談をしてみるのも一つです。
一番気を付けなければいけないのは、「どんな症状であれ自分の所へ来ていれば大丈夫」というようなことを言ってしまうところへ通うのは危険だと思います。
それではみなさん腰痛には気を付けてお過ごしください。
VBSU(バレーボールスキルアップ)ブログ






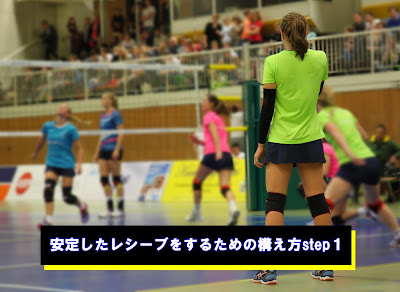

コメント
コメントを投稿