【バレーボール】レシーブで足が動かない5つの本当の理由!【あるある】
バレーボールスキルアップブログVBSUです。
このブログではバレーボール上達のための方法を勉強していきます。
読むのがめんどくさい方は聞き流しOKなこちらへ!
技術的な部分の向上のためにはどう練習やトレーニングをすれば効率が良いのかを理解し、考え実行することが大事です。
ただやみくもに指導者の言うとおりにやるのではなく、本当にそのやり方でいいのかを考えることも場合によっては必要です。
バレーボール経験者では誰しもが一度は言われたことのあるこんな
「足が動いてない!」
「足に根っこ生えてんのか!」
漫画ハイキュー!!では白鳥沢の鷲匠監督も
「足に接着剤でもついてんのか!」
と言っています。
バレーボールではフェイントや軟打などでレシーバーの前方にボー
足が動かない理由としてよく紹介されているものにスプリットステップがあります。
スプリットステップを正しく行うために身につけなければならないものがいくつもあるので、足が動かない理由はスプリットステップだけではありません。
そこで今日のタイトル
バレーのレシーブで足が動かない5つの本当の理由
こちらについて解説していきます。
まずは足が動かない理由を挙げてみます。
- 筋肉の疲労
- 予測をしていない
- 重心の位置がコントロールできていない
- そこにボールが落ちる可能性があることを知らない
- そのボールを取る気がない
これが足の動かない理由です。
足が動くようになったら次のステップとして素早く動けるように体幹の安定性や股関節の筋力を獲得しましょう!
こちらをご覧ください↓
それではそれぞれ解説していきます。
筋肉の疲労
これは長い練習や、試合でフルセットになったりラリーが続いたりすることで疲労の蓄積によって起こります。
「そこに落ちるとわかっているのに足が言うことを聞かない!」
みたいな状態になります。
解決策
筋持久力系のトレーニングや心肺機能の向上により改善をはかるこ
バレーボールの練習だけでなく、フィジカルトレーニングとしてインターバルトレーニングや筋持久力系のメニューも積極的にやってみましょう。
バレーボールの練習だけでなく、フィジカルトレーニングとしてインターバルトレーニングや筋持久力系のメニューも積極的にやってみましょう。
予測をしていない
一番多い理由はこれだと思います。
強打が来る!
そう思った時にやられるフェイントほど効果的なものはありません
強打が来ると頭で決めつけてしまうと、
なので、
そうすることで、強打が来る!
実際には瞬間的に考えることは多くあります。
相手の攻撃であれば、トスの位置や相手選手のポジショニングと助走の入り方、
解決策
常に何が起こる可能性があるかを考えて、優先順位(起こる可能性)の高いものだけでなくいくつかの可能性を残しつつプレーしましょう。
重心の位置がコントロールできていない
バレーボールはポジション取り(移動)
そのどちらでもしっかり重心の位置をコントロールして、
移動速度が遅い場合は重心のコントロールはしやすいですが、
基本的に相手がこちらのコートへボールを飛ばしてくる瞬間(
その瞬間に重心の位置が悪くバランスが崩れていると、
止まる瞬間に重心の位置をできるだけ真ん中に近い位置にコントロールできるようにします。
初めはゆっくりした動きから止まる練習をして、その時にしっかり重心をコントロールしていきましょう。
解決策
止まる瞬間に重心の位置をできるだけ真ん中に近い位置にコントロールできるようにします。
初めはゆっくりした動きから止まる練習をして、その時にしっかり重心をコントロールしていきましょう。
こちらの記事もご覧ください。↓
そこにボールが落ちる可能性があることを知らない
バレーボールではいろいろなシチュエーションがありますが、
例えば、ブロックとトス、
それを学習して様々なパターンを想定するように常に頭を働かせながらポジショニ
解決策
常にプレーをして経験を重ねることで学習していくことも大事です
そのボールを取る気がない
バレーボールのコートは9m×9mで、そこを6人で守ります。
ブロックの枚数にもよってレシーブの人数が変わったり、レセプション(サーブレシーブ)に入る人数はチーム事情によって変わります。
そのため穴になる部分が出てくるので落ちることは仕方ないのですが、ボールが落ちた場所が自分の守備範囲ではないと思いそのボールを取る気がなければ足が動かなくなってしまいます。
自分の守備範囲ではないと思ったものでも積極的に動きます。
一見無駄な動きだったり味方の邪魔をするようになってしまうこともありますが、触らずにボールが落ちてしまうことの方が問題です。
自分がボールを拾う気で積極的にプレーしてください。
解決策
自分の守備範囲ではないと思ったものでも積極的に動きます。
一見無駄な動きだったり味方の邪魔をするようになってしまうこともありますが、触らずにボールが落ちてしまうことの方が問題です。
自分がボールを拾う気で積極的にプレーしてください。
まとめ
指導者が足を動かせと言うのはボールをコート内に落とさないためにかける言葉です。
バレーボールという競技に慣れてしまえば何が問題で足が動かずにボールが落ちたのかが自覚できますが、バレーボールを始めたばかりの人やバレーボールに慣れていない人にとってはなぜ足が動かないのか自分でわからないことが多いと思います。
原因を自分で理解して練習に活かしてみてください。
バレーボールスキルアップブログVBSU






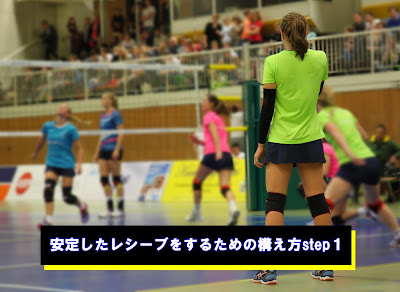

コメント
コメントを投稿